いまならPrimeVideoで、クリストファー・ノーラン監督の超大作「インターステラー」が見放題配信中。
ラストシーンの予想もできない結末は映画ファンなら必見です。
見放題配信終了してしまう前にぜひチェックしておきましょう!!


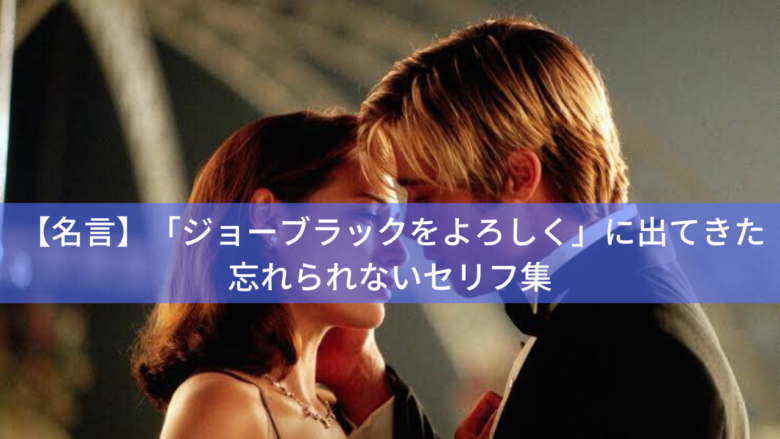

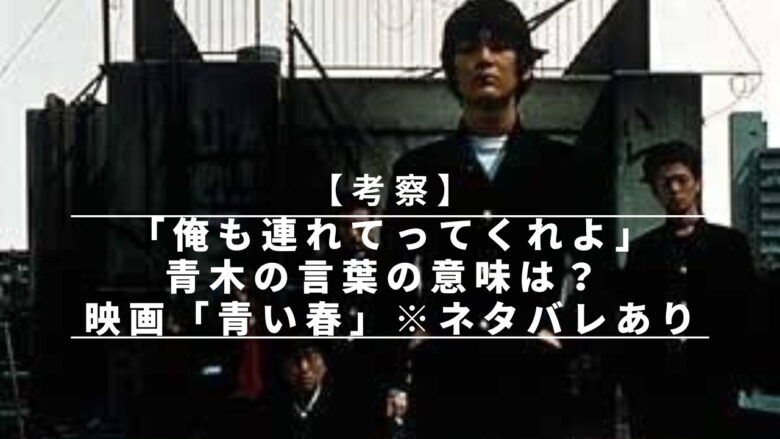



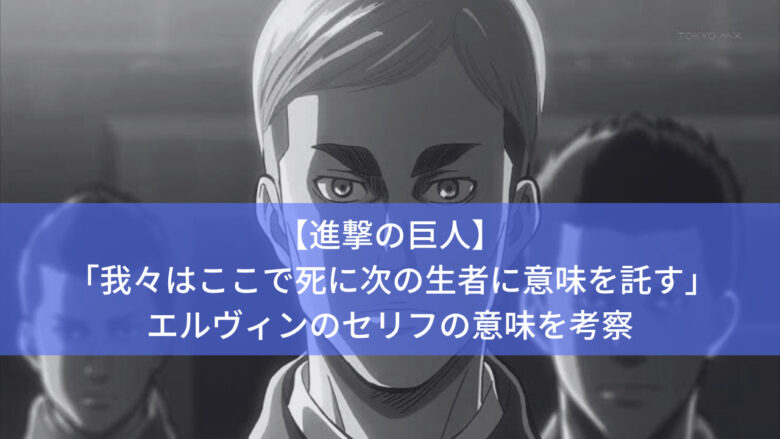
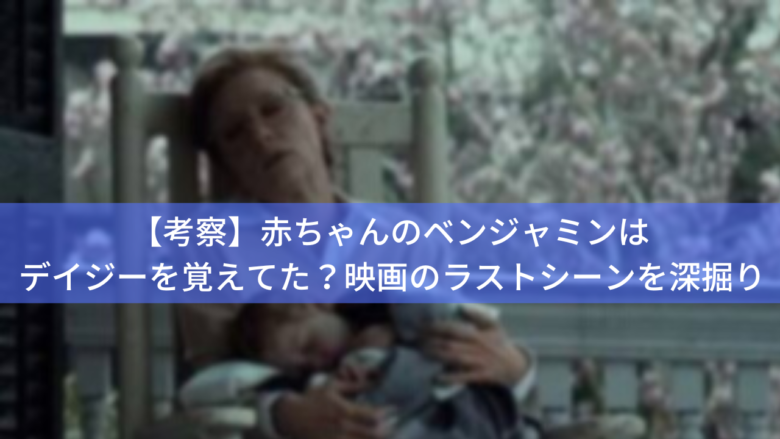
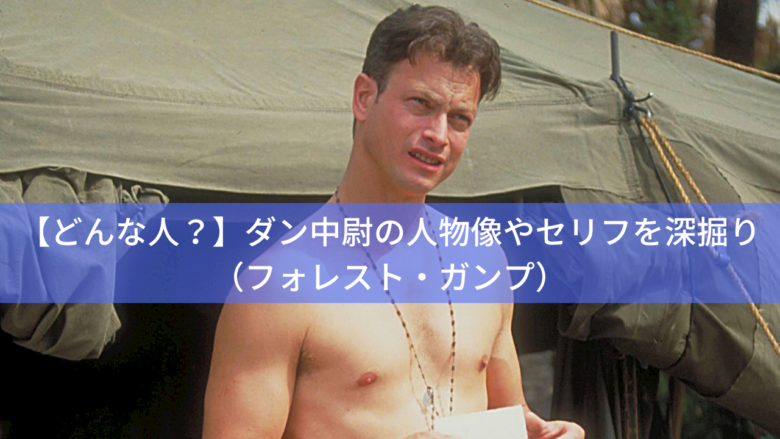

いまならPrimeVideoで、クリストファー・ノーラン監督の超大作「インターステラー」が見放題配信中。
ラストシーンの予想もできない結末は映画ファンなら必見です。
見放題配信終了してしまう前にぜひチェックしておきましょう!!
映画「ターミナル」は2004年アメリカ公開のヒューマンドラマ。監督はかの有名な名匠スピルバーグが手掛けています。
今回は本作に登場したヒロイン的存在「アメリア」が選んだ決断に関して深掘りしていきます。
本作を観た方の中には、「何故アメリアは元彼を選んでしまったのか..」と不思議に思った方も少なくないはず。
今回はそんなアメリアの選んだ決断に関して、理由を考察してみました。
▼ターミナルに似た映画をお探しの方向け


結論、アメリアがビクターではなく元彼を選んだ理由は明かされていません。
全て観た人の捉え方次第であるのは間違えないでしょう。
その為、考察はあくまでの一例としてお読みください。
第一にアメリアが単純に、ビクターより「元彼」を選んだ説が考えられます。
ビクターよりも遥かに長い時間関わっていた「元彼」の存在はアメリアの中で強かったはず。
いくら別れたとしても未練があってもおかしくありません。
寂しがりやな性格のアメリアは、元彼に特別ビザと「よりを戻すこと」を提示され、揺れてしまったのかもしれません。
少し願望的な説ですが、アメリアが自分を犠牲にしてでもビクターのためになりたかった、と考えた可能性も考えられます。
ビクターの気持ちになると、この説であって欲しいと考えるのは自然なこと。
アメリアは、自分がまた「不倫相手である元彼」の元に戻り、自身の未来を手放した代わりに「特別ビザ」を入手しています。
アメリアの気持ちが堕ちきっていなければ、ビクターに対する気持ちは嘘ではなかったはず。
親密になったビクターとアメリアは空港で出会い空港で別れを告げます。
もしかしたらアメリアはそれが「運命」だと信じていたのかもしれません。
空港には様々な人が降り立ち、通過点として次々と旅立っていきます。それは旅先なのか、故郷なのか、空港に立ち寄った人によって様々です。
そんな空港で知り合った2人の運命は、「一緒にならないこと」とアメリアは考えた可能性も高いでしょう。
とはいえ、人生は長くても短くても「出会いと別れ」の繰り返し。
本作で示していた「空港内での出会いと別れ」は、「人生の縮図」として描かれていたのかも知れません。
本作のタイトルが「ターミナル」と題されているのにも、この辺りが強く関係しているのではないかと個人的には考察しました。
トムハンクス主演の有名作品に「フォレスト・ガンプ」が挙げられますが、
ガンプとビクターの共通点は「とにかく真面目で純真」なところ。
そのまっすぐな心に周囲の人間は惹かれ、次第に仲間が増えていくストーリーはなんとなく似ている気がします。
また、「ヒロイン」的存在が自由奔放な性格の部分も似ていました。
ガンプに登場する幼馴染「ジェニー」もアメリア同様自由奔放な性格。
両者の違いとしては、「(形式的には)アメリアはビクターの元から離れる選択をした」こと。
フォレストガンプでジェニーは、最終的にガンプの元に戻ってきました。
そして、フォレストガンプのラストシーンにも似たようなシーンが登場します。
それが、息子ガンプをスクールバスに送り出した後のガンプのセリフ「ここで待ってるよ」というもの。
両作の共通点は「人生の縮図」を表した作品であること。先述したように人生はまさに出会いと別れの連続です。
取り上げた2作品の監督は同一人物では無いものの、これらの共通点は何か関係があるのかもしれません。
本作含め、映画は何度も見返すうちに「何気ないセリフに含まれた、隠された意味」のようなものが見えてくる時があります。
時にその考察が全く見当違いのこともあれば、だれも気が付かなかった考察ポイントになることもあります。
ただ、映画は観る人によって色々な解釈が出来るのも楽しみ方の一つです。
ぜひこの記事をお読みいただいた方は、見直し鑑賞をしてみて「あなたなりの考察」を展開してみてはいかがでしょうか。
お読みみいただき、ありがとうございました。
コメント